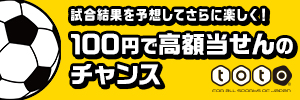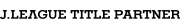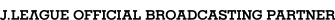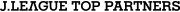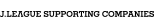試合前に確かめた時にはそれ程とは思わなかった。それを一番よく分かっていたのはウォーミングアップで水しぶきを上げながらボールを蹴っていた選手たちだろう。1日、大雨にさらされた長良川。
「学生時代には覚えがありますが、プロになってここまでボールが動かないピッチで試合をしたのは、選手時代も含めて初ですね」
大分・田坂和昭監督が綴った言葉である。それほどまでに、たっぷり過ぎるほどの水分を含んだピッチコンディション。大量の水しぶきとともにボールがピタッと止まってしまう。岐阜も、大分も、勝利を得るために入念に重ねてきた練習や戦術は、皮肉にも大雨によって意味のないモノとなってしまった。
田坂監督の言葉を借りれば「雨のサッカー」で、ラモス瑠偉監督の言い回しを借りれば「ラグビーサッカー」をやるしかない状況だった。唯一無二のキーワードとなったのは『蹴って、走る』ことと、『セットプレー』。相手の裏にボールを蹴り込み、そこに攻撃陣が猛烈なプレッシャーを掛ける。言い換えれば、自分たちに“事故”が起こらないよう前にボールを蹴り飛ばし、相手の“事故”を誘うためにそれをひたすら追う。あるいは水とは関係しにくいセットプレーからゴールを狙う。それが最も勝利に近い戦い方であり、実際にこの日の5ゴールがこのいずれかから生まれたのだった。
だが、この“割り切り”をより忠実に、より強度に、より組織的に貫徹したのが大分だった。指揮官はハッキリと指示を出していたという。
「相手の裏に蹴ればボールは止まるでしょうし、そこからプレッシャーをかける、その連続だと。その上でコーナー付近に来ればしかけるなりクロスなりという狙いを持っていた」
その狙いどおり、大分はキックオフからチーム全員でこの意図を体現。まさにその形から奪った1点目。同点とされながらも「(キム)ジョンヒョンの2点目が流れを変えてくれた」(林容平)と、セットプレーから奪った2点目。そして決勝点となる3点目を奪った為田大貴は「ウチのほうが相手より割り切ったサッカーができていたと思うし、組織的にやれた」と自負する。スクランブルな戦いにも負けない割り切りの強度、それを90分間やり切るだけの組織力があった。
岐阜の視点で振り返ると、この“割り切り”をチームで統一するまでに時間がかかった。もちろんウォーミングアップのときに芝の状態は知っていたし、チームで『ナザ(リト)を目がけて蹴ろう』という話もしていた。それでも岐阜がペースをつかんだのは後半からである。20分、ヘニキのロングボールが水たまりの影響を受けて比嘉諒人の決定機を生み出したが、前半はこのシュート1本のみ。ボールをつなごうとしてしまうシーンから徐々に立て直していく対応力は見せたものの、ナザリトを目がけてロングボールを蹴ったため、ボールが短く大分ディフェンダーは前向きで難なく対応。セカンドボールを拾われてしまった。
もちろんナザリトが競り勝つ、ボールが長過ぎることで直接GKまで届いてしまえば意味はないだろう。それでも後半の岐阜が勢いを持ってペースを盛り返したのは、相手ディフェンダーの背後にボールを送り込み、相手守備陣を後追いにさせたからである。結果的に「最初からそうやれれば良かった」(宮沢正史)という悔いを生んでしまった。
とはいえ、どちらに転がってもおかしくない試合だった。ラモス監督も「2点目が入るまでは五分五分だった」と言う。膨大な運動量を持ってハードに戦った大分の林が「最後は厳しい展開になり怖かった」と危機感を感じていたように、岐阜も決してあきらめることなく重心を前に掛け続けていった。82分にはナザリトが大砲のような、35m級の直接FKをバーに当て、後半アディショナルタイムにはその背番号9がCKから意地の2点目を奪った。
ただ、大分には印象的な光景がたくさんあった。
例えば、セットプレーを与えれば大分の選手は何人もの選手が悔しがっていたこと。例えばダニエルが忠実過ぎるほどのセーフティープレーを連発していたこと。そして得点を奪うたびに、大分の選手たちはほぼ全員が得点者を祝福に駈け寄っていたこと。いずれのシーンも、田坂監督のこの言葉とリンクしていたように思う。
「(このピッチ状況の中で勝点3を得るために)どうやってチャンスを作るのか、どうやってしのぐか。それを選手が意思を統一して戦ってくれました。もちろん課題はたくさんありますけど、いまは勝つことが我々にとって一番大切なことなので」
かつてピクシーがリフティングで沸かせたような、大雨の長良川。そこで「勝つためのサッカー」を貫いた大分は、プレーオフ圏内の6位を死守する勝点3を手に入れ、7位・山形との勝点差を『2』に広げてみせた。
以上
2014.11.02 Reported by 村本 裕太