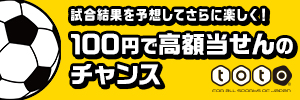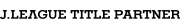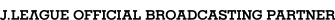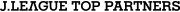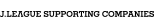矢折れ、刀尽きる。
広島敗戦の風景を例えるのなら、まさにこの言葉に尽きる。
3日前に120分+PK戦を戦い、そのまま自宅にも戻れなかった選手たちは、驚くほど、疲れていた。一歩目が出ない。球際で勝てない。いつもなら無意識のうちにやれているパスコースの創造もできないから、いつものようにボールをつなげることもできない。必然的に、横浜FMに押し込まれる形となった。こういう苦しい展開はリーグ戦の最中にもあったが、そこで我慢できる精神的な余裕が、広島の連覇を支えた。だが、この決勝戦には、体力的にも精神的にもゆとりは全くない。
横浜FMは、広島の左サイドに徹底して人材を投入して圧力をかけ、えぐるような形で突破を図ってくる。その鋭利極まりない刃を、広島は必死で食い止めてはいた。だが17分、小林祐三と兵藤慎剛、そして端戸仁と波のように押し寄せるアタッカーたちを跳ね返すことができずにボールを運ばれ、中央で待っていた齋藤学の鋭いシュートを許した。
「もっと自分が身体を寄せていれば」と塩谷司は悔やむ。悔しさ、歯痒さ、辛さ。試合後の塩谷のほほをつたう涙は、自分を責め続ける感情の表現だ。
その直後、石原直樹が右サイドからアクロバティックなシュートを放つ。だがGK榎本哲也の鋭い反応とバーに防がれてしまうと、またも流れは横浜FMに。簡単にボールを失い、左サイドのスルーパスからCKを与えてしまった。この判定、記者席でも「オフサイドでは?」と論議を呼ぶほどの微妙なものだったが、ゲームの流れからすれば、オンサイドという判定も致し方ない。サッカーとは、得てしてそういうスポーツである。中村俊輔のキックから放たれた中町公祐のヘッドが、西川周作にはじかれてもなお、中澤佑二の前に飛んでくる。それもまた、サッカーの必然的な流れである。
その後、広島は身体の奥底に眠っていた最後の力を振り絞り、「負けたくない」という強烈な気持ちが疲労を凌駕するようになって、ボールを動かし続けた。ミキッチのクロスから何度もチャンスをつくり、広島らしいコンビネーションを何度も駆使して、横浜FMのゴールに迫った。カウンターから何度も決定機を創られたが、ギリギリで身体を寄せて何とかしのぐ。
51分、高萩洋次郎のドリブルから縦パスが入り、佐藤寿人とのコンビネーションから石原が決定的なシュートを放つ。決定的だ。だが、ボールは枠の外。もし、これらのビッグチャンスを決めていれば。そう何度も、考えてみる。もちろん、試合の流れは変わっただろう。だが、勝てたか。それで、勝てたのか。わからない。「たら、れば」の話は、夢の中だ。だが、気力だけで強敵に立ち向かった彼らは、もう限界だった。走る。闘う。ボールを動かす。だけど、その全てが、少しずつズレる。結果として、一度もネットを揺らせなかった。5度目の決勝挑戦も、天皇杯には手が届かなかった。
広島から東京に到着したのが、12月28日。そこから5日間、一度も広島に戻れない。ホテルと自宅とでは、疲労の抜け具合が全く違う。その上で、120分+PK戦という厳しい戦いの後、中2日での決勝戦。「2試合連続120分の戦いも、それは自分たちの責任」と指摘する声も聞く。だが、甲府やF東京の情熱的な戦いぶりと、全力で彼らに立ち向かった広島の選手たちの奮戦を間近で見てきた者にとって、そんなことはとても、言えない。できればあと1日、余裕を与えてやりたかった。だったら広島が勝てた、などと言うつもりはない。だけど、もっと違う広島を、国立競技場で見せられたことは確かだろう。
しかし、選手たちはそういうことを一言も言い訳せず、「横浜FMは強かった」と完敗を認めた。「今日は、横浜FMに拍手を贈りたい。次に闘った時は、また違う結果になるよう、努力するだけ」。悔しさに瞳を濡らした塩谷は、再起を誓う。そして、その機会はすぐにまた、やってくる。
2月22日、舞台は再び、国立競技場。富士ゼロックス・スーパーカップで、天皇杯王者と再会するために、紫の戦士たちはしばしの休息に入る。打倒・横浜FM。2014年シーズンの大きな目標ができたことは決して、ネガティブなことではない。
天皇杯制覇を果たした横浜FMに敬意を表し、Jリーグ連覇、天皇杯ファイナリストと、素晴らしい成果を残したサンフレッチェ広島に心からの拍手を贈る。それこそ、2013年の締めくくりと新年の始まりに、ふさわしい。
以上
2014.01.02 Reported by 中野和也