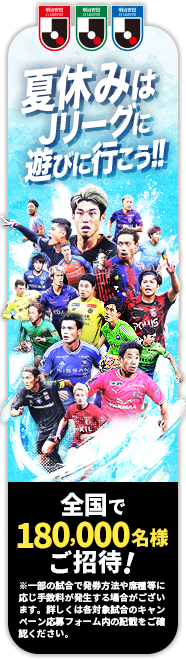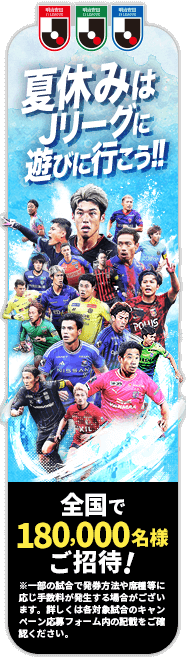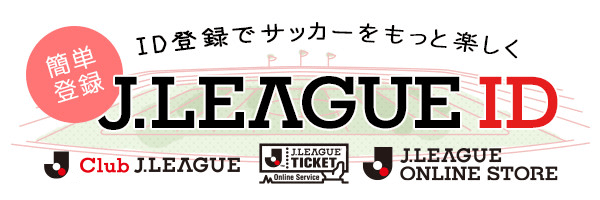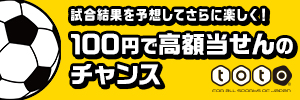2023年1月31日
2023年度 第1回Jリーグ理事会後会見発言録
2023年1月31日(火)17:30~
JFAハウス4階会議室およびWebミーティングシステムにて実施
登壇:野々村 芳和チェアマン
陪席:窪田 慎二 執行役員
青影 宜典 執行役員
勝澤 健 執行役員
大城 亨太 クラブライセンスマネージャー
〔司会より説明〕
本日開催いたしました第1回理事会後理事会後の会見を開催いたします。
《決議事項》
1.サッカー番組新設の件
https://www.jleague.jp/news/article/24542/
この度4月より30地域に拡大してサッカー番組の放送を開始いたします。こちらは昨年10月より福島、富山、愛媛、熊本、鹿児島の5地域にてサッカー番組のトライアル放送を開始していましたが、4月よりエリアを拡大し、30地域で放送を開始することといたします。このサッカー番組では全国各地域におけるサッカーの普及促進につなげるべく、サッカーをする子どもや、これからもっとサッカーに興味を持っていただきたい方々に向けて、各地域における少年少女年代のサッカー情報からJクラブの情報まで、各地域のサッカーに関する話題を幅広くお届けする番組となります。このサッカー番組の開始にあたりましては「60クラブがそれぞれの地域で輝く」というJリーグの成長戦略実現に向けた第一歩となります。サッカー番組の開始をきっかけに、各地域におけるサッカーならびにクラブの関心を向上させ、サッカーの普及促進、そして、各地域でクラブがより輝く存在にしていきたい、という想いからこの番組を立ち上げました。なお、本番組は系列を超えて30地域の民放地上波テレビ局が同じタイトル、同じコンセプトでオリジナル番組を制作する初めての取組みとなります。番組タイトルも、30地域全て「KICKOFF!○○(地域名)」という名称で統一しています。放送地域につきましてはリリース添付の通りとなりますので、ご確認いただければと思います。
2.2023年度Jリーグ配分金規程に基づくクラブ配分金額等決定の件
https://www.jleague.jp/news/article/24544/
昨年より配分金の方針につきましてはチェアマンよりご説明させていただいていますが、金額につきまして改めて公表いたします。
●基本方針
まず方針について、繰返しになりますが、Jリーグ新たな成長戦略として掲げる「2つの成長テーマ」を推進していくために、従来の均等配分金に重きを置いた配分構造から、競技成績やファン増加等の結果配分中心へシフトするとともに、それらの成果創出を後押しするため、J2、J3クラブも含めてフットボール強化やローカル露出拡大につながる施策投資原資へ振り向けていくという方針を掲げています。
目安としてJ1:J2の配分金比率を5〜6倍程度までJ1への配分割合を段階的に高めていくことを公表しています。
●主な変更点
2023年度の主な変更点といたしまして、均等配分金の総額の見直し、ファン指標配分金の増額、リーグ事業協力費の対象にJ3クラブを追加しています。
なお2023年度の改定ではございませんが、2024年度から、降格救済金の廃止、ACLサポート配分金の総額および配分方法の見直し、理念強化配分金の見直しを行なっていますので併せてご説明いたします。
●均等配分金
まず均等配分金ですが、2023年度からJ1クラブは2.5億円、J2クラブは1億円、J3クラブは2,000万円と致します。
●降格救済金
降格救済金ですが、2023年度は前年から変更はございませんが、2024年度以降の降格救済金は廃止といたします。すなわち今シーズン、2023年の順位に基づく2024年からの支払いは無しとなります。
●結果配分(競技)
続きまして結果配分・競技面です。賞金は2022シーズンと2023シーズンは同額といたします。
ACLのサポート配分金ですが、2023年度はACL出場クラブに対して1クラブ1億円を支給する、これはこれまでと変わらない方針でしたが、2024年度以降は理念強化配分金が前年J1リーグ戦1位〜9位への支給へ変更に伴い、総額を0.5億円といたします。
J1リーグ戦10位以下のクラブがACLに出場した場合は、該当クラブで按分して支給することといたします。もしも該当クラブが無い場合は、リーグ戦上位4クラブで按分して支給することといたします。
●結果配分(人気)
続いて結果配分の人気ですが、ファン指標配分金は3.4億円を増額し、総額13.4億円とし、こちらも従来通りDAZN視聴者数等で配分することと致します。
●理念強化配分金
そして理念強化配分金です。
2023年度は2020年10月のJリーグ理事会決議により、2020年度以降の順位に基づく理念強化配分金の停止を決定しているため、2023年度も支給はございません。
そして2024年度から2023シーズンの成績・順位に基づき支給を開始いたします。
まず競技順位ですが、J1リーグ戦の1位〜9位に基づき、総額約16億円を1位から9位まで傾斜をつけた形で配分いたします(リンク先ニュース表1参照)。なお1位〜3位までは2か年で支給することといたします。
人気順位の方ですが、DAZNの視聴者数等に基づいて1位〜9位まで支給を行い、総額約5億円となります(リリース表2参照)。
●リーグ事業協力費
リーグ事業協力費、toto交付金、その他につきましては記載の通りです。また配分金規定については、ホームページに掲載されている「Jリーグ配分金規程」をご参照ください。
3.Jリーグ入会要件改定の件
https://www.jleague.jp/news/article/24543/
本日の理事会において、Jリーグ入会要件の改定を行いました。すでに発表していますが、2023シーズンより、J3とJFLの入れ替えが始まることに伴い、入会要件のうち競技成績については、リーグ全体の昇降格の考え方と整合させる形で変更することを決定しています。今回の改定は、競技成績以外の要件についても、リーグ全体の考え方との整合性の観点から見直しを行うものです。
また、Jリーグの新たな成長戦略の2つのテーマである「60クラブがそれぞれの地域で輝く」において各クラブの集客施策にも注力する方針であること、そしてJ3クラブライセンス審査との重複を解消するという観点も踏まえて改定を行っています。
主な改定事項として、1点目、入会直前年度のホームゲーム平均入場者数2,000人を目標数値といたします。2点目、財務要件は収入規模(入会直前年度の年間事業収入1.5億円以上)ではなく、短期的に資金難に陥る可能性が低いかどうかという安定性を要件といたします。そして3点目、J3クラブライセンス財務基準を充足することで包含されるため、入会前年度の期末決算時の債務超過に関する要件を削除することといたしました。なおすでに2023年1月1日付でJ3クラブライセンス交付規則を改定しており、J3クラブライセンス申請において百年構想クラブであることの条件を削除しています。Jリーグ規約に記載の改定点は報道資料の通りですのでご確認いただければと思います。
4.Jリーグ百年構想クラブからの脱退に関する件
https://www.jleague.jp/news/article/24541/
本日の理事会において、ラインメール青森、コバルトーレ女川および高知ユナイテッドSCについて、Jリーグ百年構想クラブから脱退することを承認いたしました。こちらは、2022年12月の制度改定により、Jリーグ入会要件からJリーグ百年構想クラブであることが外れたことにより、これまで必須であった百年構想クラブでなくともJ3ライセンスの取得に支障がない状況となったため、当該クラブからの申請に基づき脱退を承認いたしました。いずれのクラブもこれまでと変わらずJリーグ入会を目指し、ホームタウンの自治体やスポンサーからの支援、ファン・サポーターの声援を受け活動して参ります。
5.2023Jリーグ規約規程改定の件
6.2023シーズンに関する懲罰基準の件
《その他》
1.2023シーズン担当審判員一覧
理事会の決議事項ではございませんが、例年公表しているものですので発表いたします。2023シーズンのJリーグ審判員が決定しましたので一覧にて公表いたします。
2.2023シーズンマッチコミッショナー一覧
2023シーズンのJリーグマッチコミッショナーが決定いたしましたのでこちらも一覧にて公表いたします。
なお★印が付いているのは、マッチコミッショナー委員会委員長及び委員です。
3.J3リーグコミュニケーションシステム導入について
VARもかなり浸透してきたということもあり、J1・J2では既に導入している審判員のコミュニケーションシステムをJ3でも導入することを日本サッカー協会(JFA)と共に決定いたしました。
〔野々村チェアマンよりコメント〕
本日はガバナンスを変えて初めての理事会でした。理事会で議論する時間をもっと多く取るために色々と変えてきましたが、実際に議論がすごくでき、大変面白く、変わったという感じがすごく出ていたので良かったと実感しています。
仲村広報部長から決議事項に関しての説明がありました。日本のほとんどのエリアで、その地域にあったサッカーを応援する番組が、Jリーグが投資をするという形で始まるということは、すぐにクラブや誰かがすぐに何らかのメリットを得ることももちろん必要ですが、長い目で見てサッカーをどう普及していくかということでは、無料でサッカー、また地元のサッカー少年少女、クラブの情報に触れる機会があることは間違いなくプラスになっていくと思います。協会とも色々な話をしながら一緒に作っていくことで始めていることですし、色々な意味でパートナーもついてくると思いますので、この先しっかりと続けていけるようになると良いと思っています。
加えて地域をどう盛り上げるかということでは、地域のメディアの皆様に一緒に目指していく仲間になってもらうことがすごく重要です。最近各地域のメディアの皆様と懇談をしていますが、サッカー関係者だけではなく、地域でサッカーが大好きなメディアの人をどう増やせるかもすごく大事になってくると思っています。Jリーグの中に新設されたクラブサポート本部の約50人のメンバーがそれぞれの地域に行ってクラブや地域のメディアの皆様と向き合いながら露出を増やしつつ色んな面でプラスになることを模索している段階です。これによってクラブもJリーグも双方をよく知るきっかけにもなると思いますし、これを続けることによって少し明るいサッカー界が待っているといいなと思いながら始めています。
また、声出し応援に関しては、コロナ前の形にどう戻していけるか、サッカーで言うと熱量のあるスタジアムを取り戻さないといけないという思いで色々なエビデンスを積み上げてきました。フットボール強化の側面からも多くのサポーターの熱量がある場所で選手たちにプレーしてもらうことが強化にとっても一番の近道だと思っています。早く元の形に戻せるように、かなり前に進んだとは思います。(コロナの5類への移行が正式決定される)5月8日が一つのポイントになると思いますが、それに向けて色々なことに慣れていくような環境をどう作っていくかをJリーグとしては考えたいと思っています。うまく社会が回っていく一助になれたらいいなと思いながらサッカーをつくっていきたいなと思います。
〔質疑応答〕
Q:配分金について伺います。現状約2倍のものを5、6倍にというところですが、段階的にというのはいつぐらいを目途に5、6倍にしていくイメージなのかといった点と、細かいところで、1が何で5、6が何かを詳しく教えていただけますか。
A:青影執行役員
比率に関しましては現状、方針としてJ1、トップチームを輝かせるため、競争インセンティブを設けるために配分構造を変更することにしました。その方針についてはクラブと合意をしているのですが、今年、来年、その先の配分金について、23年については決まっていますが、24年以降の具体的な配分金については再度クラブと協議し、合意をしていくので、その段階のJリーグの経営状況やクラブの経営状況を加味して決めていくことになります。今、明確にゴールは決まっていませんが、我々としましてはJリーグ全体を成長させていくためにはこういった構造に変更することが、いち早くクラブの成長にもつながると思っているので、クラブの皆さんと協議をして進めていきたいと思っています。
比率に関しましては、皆さまに大まかにイメージをつかんでいただくために、J1とJ2の比率という形で示していますが、現状はだいたい均等配分金を含めた配分金のそれぞれのカテゴリー間の比率が2対1であるところを5対1、6対1といった数字に変更していければと思います。
昨年チェアマンからも変更について説明させていただきましたが、ヨーロッパのトップリーグではそのぐらいの格差があるということも参考にしながら、Jリーグの配分構造のあるべき姿をクラブと共有して検討しているところでございます。
Q:均等配分金が5対1になるということですか?それともそのほかのことも含めてということでしょうか?
A:青影執行役員
配分金には今回復活をご案内している理念強化配分金も含まれています。これはJ1のクラブに傾斜配分としてお配りする予定のもので、人気配分のファン指標配分金も60クラブ、全クラブ対象としたものもあれば、理念強化という形でJ1のトップ9クラブを対象とした配分もあります。それぞれの傾斜配分も含めて全体として比率が6対1ぐらいを目指したいという意味です。
A:野々村チェアマン
流れや歴史があるので、最低限の配分金も確保しながら売り上げをどう伸ばすかということができたときに実現しやすいということはあります。今の売り上げのままで6対1に変更することもできなくはないですが、売り上げを伸ばして6対1に近づけていくというビジョンで進めていきたいと思っています。
Q:今の配分金の件ですが、かつて理念強化配分金があった当時、6対1以上になった年もあったのではと思うのですが、格差拡大なのか、当時目指そうとしていたところに戻ろうとしているのか、シナリオづけ等はしているのでしょうか?
A:野々村チェアマン
当時、私はクラブ側にいましたが、配分が結果的にどうだったのかという評価から話すと、リーグ側の評価としては思ったような、トップで引っ張ってくれるようなクラブが出てくることになったか、その費用がどういったものに使われたか等を精査したうえで、あのやり方ではなかったという結論から、次にどんな手を打つかといった流れになったと思っていただければと思います。いつも申し上げていますが、今のJリーグは10年前と比べると、20~25番目の売り上げのクラブと上のクラブの差が段々なくなってきており、競争の中で10年後のトップクラブを目指すクラブが、どこかいうことが分かりにくくなってきています。これは良いことでもあると思うのですが、そういう状況ならば、トップ10に入るようなクラブを目指すモチベーションが生まれるような傾斜にした方が今の段階では良いのではないかというところから、上位9位に入った場合という理論になります。
Q:その点は今までの説明からも理解していましたが、今回の配分金を見ると、どちらかというとJ1の9番目まで緩やかに傾斜配分をしているという印象を受けました。
A:野々村チェアマン
印象はたぶんそうなると思います。ただ、均等配分で今までもらえていたものをみんながもらえているかといえば、そういう状況ではなくなっています。
Q:均等配分は少し減っています
A:野々村チェアマン
今年は移行期があるので、若干多めに設定していますが、均等配分に関しては、本来であればもっと下がる可能性があります。それをどうすればいいのかということですが、勝てば、あるいは人気が出ると多くなるという世界をみんなで作っていこうということです。もしかすると今年の金額だけを見ると分かりにくいかもしれませんが、思想としてはそういうことです。
Q:今までは4番目ぐらいまで多額の理念強化配分金が出ていた時期もあったと思います。野々村チェアマンがよくおっしゃるビッグクラブを作るという発想でいうと、イメージとして持ちやすいのですが、そこからこういう形に変えていく理由がもう少し分かると伝わりやすいと思います。
A:野々村チェアマン
Jリーグが30年たって、すべてにおいて、プロフェッショナルになれているかということに関しては、まだ足りないところは当然ながらたくさんあると思います。最初の15年で選手がプロになりました。次の15年で日本人指導者がプロになりましたということが出来てきたとするならば、ここからフロントも含めてサッカー界、クラブ全体がどうプロフェッショナルになるかということを競争するような時期にならないといけないと思っています。そういう競争をしていく上で、それなりの金額があると勝てるのがサッカーです。J2であろうと、J3であろうと変わっていく可能性があるクラブはたくさんあるという、いい意味でどこが伸びていくか分からない状況の中で、いくつかのクラブが伸びる可能性を傾斜配分の中で見出し、結果的にプロフェッショナルが増えていくことを目指すのが、今のJリーグにとっては必要と考えています。
Q:地域のサッカー番組ですが、各地域によっていろいろなそれぞれの番組になっていくと思いますが、例えば15分番組なのか、1時間番組なのか、どういう形で週何回放映してもらいたいなど、どんな番組に育ててもらいたいといったビジョンや、番組のスタンダードがあるのか等、教えていただけますか。
A:野々村チェアマン
放送時間は15分もしくは30分、生放送、録画様々です。地域よって土曜日の朝もあれば11時ぐらいからの放送も多いですし、夕方もあります。それぞれの地域にある局の中の放送可能な時間で、一番効果的なところを選択しています。内容に関してはクラブがというよりは、地域の子どもたちが「あの番組に出たい」「見たい」とか、また「この地域でこんなに頑張っている男の子、女の子がいる」と思ってもらえるようにうまく表現してもらえるといいと思っています。2次利用の関係でYouTubeがどうなるかは分かりませんが、あの地域にこんな子がいるということを知ってもらえることも小さな子どもたちにとってはすごくモチベーションですし、私が小さい頃の静岡にはそんな番組があったので、私だけではなく、理事会のメンバーで(静岡県出身の)内田特任理事もそうだと思います。サッカーをやっていくうえで楽しめるきっかけになる何かが大事だと思います。見てくれる人たち、子どもだけじゃないと思いますが、大人も含めて地域のクラブに関わりたいと思ってもらえるような、子どもからすると世界への入り口は地元のクラブだということが伝わるようなものになればいいと思います。
Q:コロナの5類移行に関する質問なのですが、FUJIFILM SUPER CUPのリリースに記載されていたマスクの着用についてですが、必要なときもあるので携行してくださいと、携行という言葉で表現しています。マスクをしなくてもいいのかという受け止め方をされることもあるかと思います。これから基準を作っていくのは難しいとは思いますが、ガイドライン、基準の定め方で苦心したこと、これからどういったことに注意してやっていこうと思っていますか。
A:野々村チェアマン
5月8日までにどういった世界にしていかなければいけないか、私がどう思っているかは先ほど伝えさせていただきました。7日までダメで、8日に急によくなるということでもないと思います。サッカーの周囲でどのようなことが起こるのか、世の中で起こることがサッカーでも起こると思うので、それに対してある程度柔軟に対応できるようにした方がいいと思います。リーグが決めるというよりはクラブと地域の自治体でまずどう判断するかというところがあります。それが私の思いです。前向きに進めていこうという指示をして、その中でどういうことで難しい場面があったかは担当から話をさせていただきます。
A:窪田執行役員
前向きな表現にしたいということは考えて作りました。政府のガイドラインも変わっていますので、それに対して同じことをいうにしても、「マスクを着用してください」と、「必要な時にマスクをするために持ってきてください」では、伝わり方が違うと考えてガイドラインに落とし込みました。ガイドラインをお読みいただいているのでご理解いただいていると思いますが、100%収容ができ、マスクを着用していれば全員が声を出せるという状況です。一方で応援というよりは、一時的な発声、ゴールの時に喜ぶ等、そういうときにマスクをしてくださいというものが今の政府のガイドラインですので、そうではないとき、例えば距離が取れているなどそれぞれ環境が違うと思います。たくさん入っているスタジアムと、少し席に余裕があるところではマスクの着用をすべきか、すべきではないかということは判断できると思います。市中と同じだと思っていただき個別に判断できるようなニュアンスも含めてガイドラインに落とし込みました。少しずつ前向きに進めるようにしたいと考えています。
Q:今の関連で、改めて、11日のFUJIFILM SUPER CUPから新しいガイドラインを適用するということで、そのようなスピード感はJリーグの魅力だと思いますが、開幕前にこういう形になったことは、チェアマンとして前向きなのか、どう受け止めているのか教えてください。
A:野々村チェアマン
ようやく今のところまで来たかという思いも正直ありますが、昨年4月から準備してきたものが,一応、経営面では(入場可能数の)100%、(全席で)声を出せる人が入ってもらえるということになったという点は良かったと思います。先ほどお話したようにもっと前に進めなければいけないこともあるでしょうし、進めていく中で、いろいろな不具合が、サッカーの現場だけではなく、社会に絶対に出るはずです。繰り返しになりますが、元に戻っていく中で、サッカーが社会の一助になれるようなことをやらなければいけないと思います。前向きです。
Q:もう1点、理念強化配分金に関し、20年の10月の理事会のときに、総額が27億8千万円ぐらいだったと思いますが、今回は順位の成績とファンベースのものを足すと21億円少しだと思いますが、全体の総額に変化がある理由は。ほかのところに回しているのでしょうか?
A:青影執行役員
当時も理念強化費配分金は年度ごとに何回か見直しをしており、最終的には総額20億でいこうと合意していました。その後、コロナの状況を踏まえて途中で停止という形になってしまったのですが、改めてそのときの水準に今回戻しているのと、特にローカルの露出を高めるための施策投資にも配分していますので、そういった全体感の中で金額を決定しています。
仲村広報部長より補足
ただいまの質問で「3年でそのシーズンからそれ以降もらえる総額が27.8億円」という話なので、比較対象としては確かに異なると思います。
Q:東京都葛飾区が23区内サッカー専用スタジアム建設に向けて用地取得する方針を発表しました。Jリーグも23区内スタジアムという形で構想があったと思います。今後どうなるかは推移を見守るほかないのですが、南葛SCの地元でもありますし、改めてそういう動きが東京23区内で出てきたと言うことに関して所感があれば教えてください。
A:野々村チェアマン
私個人の所感ですが、想いのある人たちがいて、実際にいろいろなことを動かしてここまでたどり着いたというのは、サッカーにとってすごく良いことだと思います。
都内でサッカースタジアムをと考える人たちにとってもとても大きな一歩になるのかなと思っています。
Q:Jリーグも23区スタジアム構想、準備室を発足させていて、今回の葛飾区の動きと連動、影響を受けて考え方を改める、できる限りの協力体制をしていくなど動きの影響があれば教えてください。
A:大城クラブライセンスマネージャー
葛飾区の件に関してはJリーグ側の23区スタジアムの働きかけというよりは、南葛SCと葛飾区の連携で進んでいたプロジェクトです。我々は東京以外でも色々な地域でスタジアム推進の取り組みを行っていますが、同じように区やクラブとコミュニケーションをとってサポートしている状況です。
現在リーグが目指している23区スタジアムは、特定のクラブというよりはセントラルスタジアムという構想で、様々なイベントでも使えるような高稼働率のスタジアムを23区内にというプロジェクトで、南葛のものとは別にリーグとしては取り組みを進めています。まだお話しできるような成果があるわけではありませんが、ステークホルダーの皆様と意見交換し、旗を下ろさずにしっかりと進めていきたいと思っています。
Q:今年からユニフォーム規程が緩和されて、背番号がある程度自由に50番を超える番号も選べるようになりました。背番号は選手の顔という側面も踏まえて、もともとJリーグの選手であったチェアマンに変更の意図や、99番、57番など大きい番号をつけるという選手が増えてきた現状で背番号緩和の期待をお聞きしたいです。
A:野々村チェアマン
色々な人が出てくるのは面白いと思うか、わかりにくいと思うか、それぞれの価値観ですが、変えようと思った理由を窪田からご説明します。
A:窪田執行役員
クラブのニーズがあったからです。当然毎年規約を見直しており、ユニフォーム要項の改定も毎年行なっています。50番以降は連番、そのルールは必要なのかという議論があり、選択肢が増えるのであればクラブのニーズにお応えする形で緩和をし、55番、77番など皆様の目にとまるような背番号をつける選手が出てきたと思っています。
Q:ニーズはこれまでもあったニーズだと思いますが、それがなぜ今のタイミングで変更となったのでしょうか。
A:窪田執行役員
特にこれまで制約をしていたわけではなく、今回の議論の中で出てきたとご認識いただければと思います。
Q:確認になりますが、当初から審判員に女性が3名いらっしゃるのは初ですか。
A:仲村広報部長
女性の審判員3名の登録は初で最多の人数となります。
Q:山下 良美主審はワールドカップを経て今年も担当審判に名を連ねていますが、それを踏まえて、女性審判に対して今後こうなってほしいという思いがあれば教えてください。
A:野々村チェアマン
現場も含めて女性だから、男性だから、とは考えていません。いかにゲームをうまくさばいてくれるか、一緒に良いものを作ってくれるかを期待します。
Q:45の都道府県でサッカー番組が始まることを個人的に大変うれしく思っておりますが、今後、テレビの地上波に関してどのような考えを持っているのでしょうか。今後、地上波でもこの流れを拡大していく考えはあるのでしょうか。また、(サッカー番組制作にあたって)投資した規模、金額をお答えいただければと思います。
A:野々村チェアマン
地上波に関しては、当然放映権の契約がありますが、今の契約の中でも何本まで、何パーセントかまでは、地上波で放送できることになっています。
東京での地上波をイメージしておっしゃっているのだと思いますが、キー局での放送もリミットまでできるようにしたいと思っていますが、60クラブの地域の地上波放送をどのくらい増やせるかがクラブには最も重要なこととなりますので、そちらも増やしていく前提で番組も地域のメディアの仲間も作っていくこととしています。地上波放送は、それなりには、それぞれの地域の中で増やしていくことになります。
Q:投資規模、投資額はお答えいただけますでしょうか。
A:野々村チェアマン
投資額についてのお答えは控えさせていただきます。番組を始めるにあたっては当然Jリーグが一定の金額を用意しないと始められないので投資はしますが、番組を良いものだと思ってくださった方がスポンサー・パートナーとしてたくさん集まってくれつつあるので、リーグの投資を回収しつつ、世の中のために良いものを作っていくという流れになっていくのではと思っています。
Q:個人的願望なのですが、J1、J2、J3の試合が終わった後に、その週のよいゲームのゴールシーンが全局に流れないかなと願望として思っています。番組の内容は、Jリーグとキー局、地方局の方が考えるのでしょうか。ゴールのハイライトなり、キーパーのハイライトシーンなり、最近テレビのニュースでも良い試合があっても映像が流れていないので、そういう映像が流れたらよいなと思っています。
A:野々村チェアマン
J1のトップレベルを想定していますか?
Q:J1、J2、J3を想定しています。
A:野々村チェアマン
その地域のクラブがプレーした良い試合は、当然その地域の番組ではたくさん出てくると思います。
Q:J1のトップレベルの試合は?
A:野々村チェアマン
それはキー局の全国ネットでどのように作っていくかと思いますが、それについても原資をそれなりに用意して、投資できるようにしています。
A:勝澤執行役員
サッカー番組の内容についてご説明いたします。
放送の時間帯は、土、日が基本となります。こういった番組を見てからスタジアムに来ていただきたいという想いで、北海道から沖縄まで放送する予定です。まだ番組が確定している情報ではありませんので、現在お見せしている時間は変更になる可能性があります。
番組の内容については、Jリーグの選手の紹介や、次の試合の見所、試合の集客に向けてスタジアムでのイベント、また地域の子どもたちにとっても楽しみな番組になってもらいたいことで、子ども向けのコンテンツとして、双方向で投稿していただいたり、小中高の地域のサッカーをしている人たちを取りあげたり、シニア層や障害がある方がサッカーを楽しんでいる様子も取り上げていきたいと考えています。
現在、先行して5地域(福島、富山、愛媛、熊本、鹿児島)でトライアルをしていますが、こちらの番組はJリーグ公式YouTubeでも配信していますので、皆様ご覧いただければと思います。
Q:Jリーグ百年構想クラブについて。J3ライセンスの取得に必須ではないとのことで脱退するクラブが3つあるとのことですが、百年構想クラブの位置づけに変更があるのでしょうか。また脱退することでメリットはあったのでしょうか。
A:大城クラブライセンスマネージャー
百年構想クラブはJ3への入会要件必須ではなくなったので、この3クラブは脱退を決断されたということです。それぞれクラブによって事情が異なりますし、クラブごとにリリースされるとのことなので、そちらをご確認いただければ正確な理由がわかると思います。
百年構想クラブという制度は、年会費をお支払いいただき、我々が一定の研修メニューを提供する形でコミュニケーションをとらせていただいていました。メリットというと表現が違うかもしれませんが、年会費を支払う必要が無いというのが脱退理由の一つだと思います。
今回百年構想クラブという制度を見直すにあたって、既存の百年構想クラブといろいろ意見交換をいたしましたが、今回脱退されるクラブは百年構想クラブという看板が無くても、地域とのコミュニケーションができています。例えば女川の場合はスタジアムもほぼJ3基準のスタジアムを用意していますので、百年構想クラブという後押しが無くてもしっかりと準備を進められるとご判断されたのだと思います。
Q:百年構想クラブ自体は今後も続くのでしょうか。
A:大城クラブライセンスマネージャー
そちらについては今まさに検討しているところです。入会要件ではなくなりましたので、今のような形でずっと続けていくのか、名称をどうするかも含めて今年検討していくテーマだと考えています。
Q:今上をめざそうとしている地域のクラブもいくつかあると思いますが、何を目指すかということはまだ確定していないということでしょうか。
A:大城クラブライセンスマネージャー
J3に向けたステップは、これまで大きく3つのステップをご紹介しています。1つ目はJリーグ百年構想クラブに認定されること、2つ目はJ3ライセンスが交付されること、3つ目が入会審査に合格することです。この一つ目が必須要件でなくなりました。J3ライセンスの交付と入会審査の合格は今後も続ける予定です。
将来Jリーグ入りを目指すクラブの皆様は、J3ライセンスを申請するためにJFLに所属しなければなりません。競技成績を残してJFLに昇格し、そのうえでJ3ライセンスの申請を目指すというのが最初のステップとなっています。
将来Jリーグ入りを目指すクラブには、百年構想クラブを必須要件から外すことについて、随時理事会で決まり次第お伝えしていました。(百年構想クラブに)手を上げたいクラブはあったのですが、今回必須でなくなったので、まずはJFLに昇格してJ3ライセンスを目指すということで考えていらっしゃると伺っています。
Q:ファン指標配分金の決算のやり方をもう少し詳しく教えてください。例えばユーザー数とか、どういう数え方、その詳細はどこまで公開されるかなど。
A:広報部仲村
こちらはリリースにも記載されている通り、DAZN視聴者数等ということでご理解いただければと思います。
Q:百年構想クラブから脱退した事を受けて、今後の百年構想クラブ指定はどういう仕組みになりますか。
A:広報部仲村部長
先ほど大城マネージャーよりご説明した通り、百年構想クラブの在り方および指定の方法については今後検討していくとのことでご理解いただければと思います。
Q:リーグ入会の変更について:決議の時期が「11月」から「無指定」になったが、大体いつ頃に決議が行われますか。
A:広報部仲村部長
昨シーズンも同様でしたが、すでに順位要件がある程度確定した段階で決議が行われることが通年でしたので、時期を「無指定」としています。
A:大城クラブライセンスマネージャー
一昨年までは、JFLシーズン終盤の11月の理事会で決議していました。それは順位要件、入場者数、売り上げなど、定めていた要件の確度が高まってくる時期となるためです。
ある程度Jリーグ入会に向けた準備を早く始めていただきたいこともありますし、現場で順位要件が決まったときに喜んでいただきたいという考えもあり、昨年10月の理事会で早めに入会を決議しました。今年も同時期に決議して、成績が決まり次第入会も決まる形にできればと考えています。