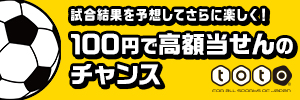元日本代表MFを父に持つ水沼 宏太にとって、サッカーは生まれた時から身近にあった。

「気付いたら、ボールを蹴っていましたね。もう、歩き始めた頃にはボールを蹴っていたみたいですよ。父は始めさせたという意識はなかったらしいんですが、家にボールが置いてあったので、始めさせたんだろうなと(笑)。僕のサッカー人生は、間違いなく父の影響が大きいですね」
1993年5月15日、Jリーグが開幕したその日、水沼は横浜マリノスに所属する父・貴史の雄姿を観るために、国立競技場の観客席にいた。

「まだ3歳だったのであまり記憶はないんですが、客席で旗を振っていた記憶はあります。試合内容は特に覚えていなくて、父が絡んだ決勝点も覚えていない。だけど、あとから見返したら、すごく激しい試合だったなと」
幼稚園の頃からサッカー教室に通い、小学校2年生からは地元の少年団に入団。すでに引退していた父から指導を受けたことはなかったが、一緒にボールを蹴るなかで学ぶことは多かった。
「こうしろ、ああしろというのはなかったんですが、一緒にボールを蹴っている時は、サッカー上手いなぁ、キック上手いなぁとは思っていて。当たり前ですけどね、サッカー選手なんだから(笑)。見よう見まねでやっていた部分はありますけど、何かを強制されたりすることはなかったですね」
父がサッカー選手であったことは、水沼にとって誇りだった。
「小学校の時に僕が所属していたあざみ野FCというチームは、お父さんコーチが指導する街クラブでした。そこにたまに父も来てくれてプレーを見せてくれるんですけど、すごく上手いのでやっぱり誇らしかったですよ。俺のお父さんはすごいんだ、って思っていましたね」
一方で成長するにつれ、父の存在が重荷に感じられることもあったという。
「中学や高校上がると、やっぱり周りの目が気になるくらい父の名前が出てくるようになって。『息子』とか『ジュニア』とかって言われたりして、なんで自分の名前で呼んでくれないんだろうという葛藤はありました。ただ、それはサッカー選手の息子としての運命だというのは、小さい頃から両親からも言われていました。そういうことを言われたとしても、宏太は宏太だから、自分らしくいればいいとも言ってくれました。だから周りに何か言われるから親が嫌いになるということはなかったし、そうやって言ってきてくる奴を見返したいという想いでここまでやってきたところもあります。プレッシャーを感じるのではなく、逆にパワーに変えるくらいの気持ちでやっていましたよ」
だから、父に対してはリスペクトの想いしかない。
「父としても尊敬しているし、同じ職業でトップにまで上り詰めた尊敬する先輩でもある。怒られたことはほとんどないですし、何でも話せる人。当時も今も仲は良いと思います」
中学に上がると水沼は、父が所属したクラブのジュニアユースに加入する。プロを身近に感じられる環境に身を置くなかで、自分もプロを目指すという気持ちが次第に高まっていった。
「小さい時から憧れていたチームのエンブレムを付けて試合をできるようになったのはうれしかったですね。中学生の時はJリーグの試合のボールボーイも担当しましたし、間近でプロの選手たちに関わることが増えていくなかで、プロになりたいという気持ちは強くなっていたと思います」
もっともその想いとは裏腹に、ジュニアユース時代の水沼は思ったような成長曲線を描けなかった。
「試合にもなかなか出られなかったし、思うようなプレーができなかったので、ユースに上がれないと思っていました。父もプロは厳しいと思っていたそうです。だから高体連のチームに行って、サッカー漬けの毎日を送ろうと思っていました」
ところが、周囲の指導者たちは可能性を感じ取っていた。監督やコーチ陣は水沼を高く評価し、ユースチームへの昇格を決めた。
「あそこで上がれたことは、本当に大きかったですね」
とはいえ、ユースに昇格しただけで、将来を約束されたわけではない。水沼はここでももがき苦しむことになる。
「1年生の時はAチームに行ったことがなくて、やっぱり厳しいかなと思っていました」
そんな水沼に転機が訪れる。1年生だけの大会が行われ、そこでハイパフォーマンスを披露。そのプレーが視察に来ていたU-15日本代表関係者の目に留まり、代表チームに選出されることになったのだ。
2007年のU-17ワールドカップを目指したそのチームには、全国から優れた選手たちが集まっていた。その中でもひときわ目立っていたのが、柿谷 曜一朗(現名古屋)である。
「曜一朗は高校2年生の時にはプロ契約をしていましたからね。みんなは高校生なので制服で集合するんですけど、ひとりだけスーツだったし、髪の毛も染めていていましたね。でも一緒にプレーするなかで、こういう奴がプロになるんだなと思いましたし、曜一朗には刺激をたくさん受けましたね」
水沼は継続的に代表に呼ばれていたものの、レギュラー獲得には至っていなかった。ワールドカップ出場権をかけたAFC U-17アジア選手権を控えた時点でも、立場は変わらなかった。
大会が幕を開けると、日本は初戦に快勝を収めたものの、第2戦はドロー。すると決勝トーナメント進出をかけた韓国との第3戦を前に、水沼は突如キャプテンに指名される。そして韓国戦では見事に2ゴールを奪い勝利に貢献。決勝トーナメントでも結果を残し、大会MVPに輝いた柿谷とともに、アジア制覇の立役者となったのだ。

「キャプテンを任された時は、なんで?と思ったんですが、決勝トーナメントに上がって、ワールドカップの切符を手にして、優勝して、優勝カップを掲げるところまで行ってしまったわけです。大会前はそんなことは想像してなかったですし、まさかキャプテンになるとも思っていませんでした。でも、その経験は大きな自信になりましたし、今まで『水沼の息子』という風に見てきた人たちを見返す気持ちでやってきたなかで、結果を残せたことは本当に嬉しかったですね」
ジュニアユースでも、ユースでも、そしてこのU-17日本代表でも、水沼は初めから特別な選手だったわけではない。しかし、大事なところでしっかりとアピールし、自らの道を切り開いてきた。
「僕のキャリアを振り返ると、そういうシーンが多くて。最初からレギュラーで出られることはあまりなかったですね。躓いて始まるキャリアのなかで、危機感をパワーに変えられる“スイッチ”みたいなものがあるのかなと思います」
試合に出られない状況が続けば、ともすれば腐って終わったとしてもおかしくはない。しかし、水沼は常に前を向き、地道な努力を続けてきた。
「そこは性格的なところはあると思います。常に前向きに物事を考えてやってきました。辛い状況も明るく乗り越えよう、きっとこの出来事には何か意味があるんじゃないかって。前に進むために起きたことなんだとポジティブに考えることができていたので、乗り越えることができたと思います。だからこの性格には、感謝していますね」
アジアを制し、翌年には世界大会も経験した水沼にとって、次なる目標はプロになること以外に他ならなかった。そしてU-17ワールドカップ終了後にトップの練習に参加し、プロ契約を勝ち取った。
高校3年時に2種登録された水沼は、プロ入りを前にして、Jリーグデビューも飾っている。対戦相手はヴァンフォーレ甲府だった。その際にも水沼の“スイッチ”は作動した。

「トップの練習に参加したんですが、めちゃくちゃ調子が良くて、練習試合でもゴール決めたり、アシストができたんです。そうしたら、次の試合にメンバー入りして。嘘だろと思いながら、甲府に行ったのを覚えています」
もっともわずか8分の出場に留まったデビュー戦のことはあまり覚えていない。しかし、試合前の出来事は今でも鮮明に脳裏に焼き付いている。
「当時、父がコーチだったんですよ。それで試合前のアップの時に一緒にボールを蹴ったんです。初めてのJリーグの試合で、その会場で父とボールを蹴り合った。後にも先にもできないような経験ができたことは、今でも忘れられないですね。まあ、僕以上に父が喜んでくれたのかなと思いますけど(笑)」
翌2008年、晴れてプロサッカー選手になった水沼だったが、ここでも躓きからの出発となった。
「高校生の時から試合に出ていたので、プロに入ったらもっと試合に出られると思っていたんです。だけど甘くなかったですね。ナビスコカップ(現ルヴァンカップ)には出してもらいましたけど、リーグ戦では途中出場が多くて。試合の数ではそこそこですけど、時間に換算すれば、そんなに出られなかった(10試合・257分)。厳しい世界だと思いましたし、もっと頑張らなければといけないと思った記憶があります」
しかし、その想いとは裏腹に、プロ2年目も12試合・217分の出場に留まった。そして迎えたプロ3年目の2010年7月、水沼は生まれた時から近くにあり、ジュニアユースから所属した横浜FMを離れる決断を下した。新天地に選んだのはJ2の栃木SCだった。
水沼の決断を後押ししたのは、その年に開催された南アフリカ・ワールドカップの光景だ。
「ワールドカップを見ていて、なんでプロになったのかを考えたんです。こういうところを目指して、この舞台に立つためなんじゃないかって。そのためには試合に出なければダメだなと思って、栃木に行くことを決めました。それまではプライドみたいなものや、変な自信もあったんですけど、それを全部壊さなければいけない。これでダメだったらプロが終わるというくらいの気持ちでしたね」
当時20歳の青年はすべてをなげうつ覚悟で、知り合いもいない、環境も分からない栃木へと向かったのだ。そして、その新天地で水沼に大きなターニングポイントが訪れることになる。
後編はこちら>>
今の自分を作った松田監督との出会い。紆余曲折を経て実現した“憧れのチーム”への帰還
取材日:2021年12月5日