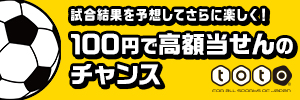ここに1枚の写真がある。

眼鏡をかけた坊主頭の少年が、首から財布のようなものをかけ、大きな荷物を背負っている。がっちりとした身体つきにわずかにその雰囲気を残しているものの、この少年がこれからオランダに渡り、後にプロのサッカー選手になるとは、この写真からは想像することはできないだろう。
高校を卒業したばかりの千葉 和彦は、プロサッカー選手になる夢を諦めきれず、オランダでその夢を追いかけることを決めていた。この写真は関西国際空港からオランダ行きの飛行機に搭乗する直前に母親が撮影したものである。
「母親が見送りに来ていた弟との2ショットを撮ろうとしたんですけど、高校生くらいだと、そういうのって恥ずかしいじゃないですか。だから断って、無理やり1人で撮られた写真が、これです(笑)」
羞恥心だけではなく、そこには寂寥感があったのかもしれない。あるいはこれから始まる日々への不安や希望も備わっていたはずだ。坊主頭少年の、ちょっぴりコミカルで不愛想なその表情からは、そんな背景が読み取れるのだ。
北海道岩見沢市で生まれた千葉がサッカーに目覚めたのは小学1年生の時だった。
「ちょうどその頃にJリーグが始まったので、自然とやっていた感じです。ただ、当時はサッカーをやる子が多すぎて、少年団には3年生にならないと入れなかったんですよ。だから、2年生までは水泳教室に通っていて、そこで体力的な基盤はできたのかもしれないですね」
3年生になると、サッカー漬けの日々が始まった。夏場は屋外でプレーできたが冬は積雪のため、体育館でフットサルのトレーニングをこなした。
「それで足技が磨かれましたね。今ではもうさびついちゃいましたけど(笑)」
冬になればスキーやスケートも楽しむ活発な少年だった。そして今の千葉の原点とも言えるお調子者の側面も……。
「参観日に親が見に来ると、勢いよく手を上げて『わかりません』と言うタイプ。今とまったく一緒ですね。やっていることは(笑)」
千葉が加入した釧路富原FCは地元では強豪と言われるチームだった。釧路地区の大会では常にベスト4以上に入り、道大会にもコンスタントに出場。当時の千葉はFWで、恵まれた体躯とスピードを武器に、本人曰く「点取り屋だった」という。
中学入学のタイミングで、父親の転勤で三重県に移り住むことになったが、そこでも当然、サッカーを続けた。
「引っ越した先の隣の家が、クラブチームの監督さんで。たまたま家に北海道のチームのTシャツを干していたら誘われて、そのチームに入りました」
中学時代もFWとして際立った活躍を見せていた千葉には、いくつかの高校から推薦の話があり、その中の一つである三重高校に進学を希望した。三重高校に入学していれば、後にサンフレッチェ広島でチームメイトとなる水本 裕貴と同級生になっていたはずだった。
「監督さんも来てほしいと言ってくれていたんです。内申点が5教科で16以上あれば、推薦してくれると。でも僕はオール3だったので15しかなくて(笑)。推薦できないから一般で受けてくれと言われたんです。だけど一般入試だと自信がないから、三重高校は諦めました。それで、どうしようと思っていたら、先生から日生学園第二高校(現青山高校)というサッカー部に力を入れ始めた学校があると聞いて、練習参加を経て特待生として入れることになったんです」
しかし早々に進学を決めた千葉だったが、その高校の情報はほとんど持っていなかった。
「今みたいにネットもないので、どういう高校か分からずに決めてしまったんです。それで周りに聞いたら、あそこはやばいところだぞと(笑)」
聞けば、その学校のOBであるお笑い芸人が、高校時代の厳しかったエピソードをネタにしているというではないか。「便器を素手で洗わされた」とか。
「そんなやばいところに入るのかと思ったら、気が滅入りましたね」
実際に入ってみると、確かに「やばい」学校だった。
「さすがに僕の時はトイレを素手で洗うことはなかったですけど、オブラートに包んで言えば、お叱りを受けながら鍛えられましたよ(笑)。ただ、今思えば愛情はあったと思います。あの環境で、あの仲間たちがいなければ、今の僕はなかった。その意味で、いい時間を過ごさせてもらったと思っています」
高校は全寮制だった。寮は山の中にあり、まさに隔離された環境だった。朝5時に起床し、6時から朝練。放課後も遅くまで練習に明け暮れた。そんな過酷な生活に、厳しくて逃げ出してしまう生徒も少なくなかったという。
「1年生が入ってきても、1、2か月くらいで逃げちゃうんですよ。それを僕らは『ダツる』と呼んでいました。『あ、今日も1人ダツったな』と(笑)」
「ダツる」生徒がいると、サッカー部員たちは捜索に行かなければいけなかった。
「でも、寮は山の中にあるので、逃げちゃうと絶対に見つからないんです。それでも先生からは探しに行けと言われるので、みんな探しに行ったふりをして、その辺で寝てました。朝練がなくなるのでラッキーでしたよ(笑)」
どれだけ山の中にあるかと言えば、早朝に鹿と遭遇することもあったというほど。町からは遠く離れているため、気軽にコンビニに行くこともできなかったという。
「事前に申告すれば、床屋には行けるんです。歩いては行けないので車で送ってもらうんですが、その時に寮母さんだと、帰りにコンビニに寄ってくれました。でも、先生の時だと、絶対に寄ってくれない。一般の高校生のようなことは一切できませんでした」
唯一の楽しみは試合の遠征だった。
「その時だけ、“下界”の飯が食べられるんです。パーキングエリアの飯が本当にうまかったですね。それが楽しみで、遠征に行っていたようなもんですよ」
ただし、遠征先は着いてみるまで分からなかったという。
「先にどこどこに行くと言うと、親に伝わって、試合を見に来ちゃうじゃないですか。先生からすれば、親が見に来れば私情が入っちゃって、その子を出してあげなくてはいけなくなる。それをしたくないからと、絶対に教えてくれませんでした。だから遠征の時は、バスが学校を出て右に行ったら、静岡方面。左に行ったら大阪方面。それを確認してから寝てました。着くまでどこに行くか分からないなんて、お笑い番組のドッキリ企画みたいな感じでしたよ(笑)」
普通の高校生活を送れない、まさにサッカー漬けの日々。ただ、そんな厳しい生活も千葉は「ダツる」ことだけはしなかった。
「当時は辛かったですけど、それよりも先生に負けたくないという気持ちのほうが強かったですね。今思えば愛だったのかもしれないですけど、当時はぼろくそに言われていましたから。練習は厳しかったし、腹が立つこともありました。だけど、そこで逃げたら終わり。絶対に見返してやるという想いだけでやっていたと思います」
その指導に賛否両論があるかもしれない。ただ、成果は確実にあった。千葉が高校2年生の時、強豪・四日市中央工業高校を破り、全国高校選手権に初出場を決めたのだ。
「先生は自信があったみたいですね。練習試合でも強豪校と互角にやれていましたし、四中工も僕らを恐れていたと思います。なにせ、情報がありませんから。あの山の中で何をやっているのかって、不気味だったでしょうね」
千葉にとっては高校時代にボランチにコンバートされたことも大きかった。
「FWで入ったんですけど、お前は長いボールを蹴れて、体力もあるからボランチをやってみろと。そこからボランチをやるようになって、県選抜にも選ばれるようになりました」
傍から見れば地獄のような3年間だっただろう。それでも千葉にとってのこの3年間は、かけがえのない記憶として刻まれている。なかでも一番の思い出は、選手として成長できたことでも、全国大会に出られたことでもない。
「一番印象に残っているのは寮生活ですね。厳しかったですけど、一緒に馬鹿なことをやれる仲間たちがいたから、乗り越えることができた。最終的に16人残ったその仲間たちと3年間やってこられたのは自分の中での財産ですし、今でも仲間に困っている奴がいれば助けてあげたい。そこの絆は強くあります」
一方で、漠然と思っていたプロサッカー選手になるという想いは、叶えることができなかった。
「後から聞いた話では、いくつかのクラブのスカウトが注目してくれていたみたいですけど、具体的な話はなかったですね。だから、自分の中で、プロになれないのかなと感じていました」
大学に進学し、プロを目指す道もあっただろう。しかし千葉にはその選択肢がなかった。
「こんな高校生活を送った後に、自由な大学生活を味わったら、絶対にやばいなと。反動が怖かったんですね。間違いなく遊んじゃうだろうし、そんな状態になれば、100人以上も部員がいるなかで、11人に入るのは難しいなと思ったんです」
可能性を求めたのはオランダ行きだった。実は千葉は高校時代に、春休みや夏休みを利用して、オランダのチームの練習に参加した経験があった。
「まったく知らない土地ではなかったし、知っているチームでもありました。プロになれないとなった時にオランダに行くという道もあるよと言ってもらったこともあって、プロになるには大学に行くよりも、自分にとっては近道だと考えました」
加入したのは、当時オランダ2部リーグに所属したAGOVVアペルドールン。もちろん、プロ契約ではなく、アマチュア選手としての参加だった。ところが単身でオランダに渡った千葉に、いきなり試練が訪れる。
「オランダに行って、すぐに盲腸になっちゃったんですよ。めちゃくちゃお腹が痛かったので医者に行ったんですが、オランダに来たばかりで食べ物が合わないだけだからって、適当にあしらわれてしまって。でも、自分では絶対に盲腸だと思ったので、持ってきた辞書で『盲腸』という単語を調べて『Appendix!Appendix!』って何回も叫んだら、やっと検査してくれて、そのまま緊急手術ですよ(笑)。後にも先にも、あんなに痛いのは初めてでしたね」
試練は続く。盲腸から復帰した最初の試合であごを骨折。そこから3か月ほど戦列を離れた。
アマチュア選手だった千葉には、当然給料は発生しない。親からの仕送りだけで生活費を賄った。食費も節約しなければならず、毎日自炊した。ただ、栄養に対する知識がなく、今のようにネットで調べることもできない。我流で挑戦したものの、上手くはいかなかった。
「とりあえず野菜だろうと。あと身体を動かすにはご飯かパスタだなと。レパートリーは、パスタが2種類とチャーハン3種類。このローテーションを繰り返していたら、ぶくぶくと太っちゃいました(笑)。そりゃそうですよね。炭水化物ばかりを食べて、たんぱく質はゼロですから」

食事だけではない。異国の地での孤独な生活は、千葉のメンタルを大きく揺さぶった。
「友達もいないし、日本人もいない。チームメイトはいますけど、細かい部分までは伝えられないので、心を許せる仲間はいませんでした。そいう環境だと、どうしても自分と対話する時間が長くなるんですよね。プロになれると思える日もあれば、このままではダメかもと考え込んでしまう日もある。心の浮き沈みの連続でしたね」
練習がある日はまだよかった。監督やチームメイトとコミュニケーションを取れるからだ。苦しかったのはオフが続いた時。何日間も、誰とも話せない時間があったという。
「今のようにスマホもなければ、ゲームもない。何冊か本を持って行ったんですが、一気に読んでしまったら、後から読むものがなくなるので、1日3ページずつとかのペースで読んでいましたね。ひどい時はやることがなさ過ぎて、当時のガラケーで47都道府県の地名を漢字で打ち続けるとか、魚へんの漢字をどれくらい打てるかとか、一人寂しく部屋にこもってやっていましたよ。ちょっと危ない状態でしたね(笑)」
それでも、日本に帰りたいという気持ちは起こらなかったという。
「このままでは帰れないと思っていました。試合には少しずつ出られるようになりましたけど、当時のオランダではEU外の選手には最低年俸が決まっていたんです。その額を払えるクラブからオファーをもらえるまでは日本には帰らない。その想いだけで、やり続けました」

しかし、結果的に千葉はオランダでプロ契約を手にすることはできなかった。日本を離れて1年半、オランダのシーズンオフの時期にJクラブの練習参加の機会を得ると、その中の一つだったアルビレックス新潟から、プロ契約の打診を受けるのだ。
「2回くらい練習参加させてもらって、契約の話をもらいました。もう少しオランダで挑戦したい気持ちもありましたけど、親には経済的な負担をかけていましたし、日本でプロになるのが一番いいと判断して、新潟入りを決めました」
過酷な高校での3年間と、1年半の孤独なオランダ生活を経て、千葉はついにプロサッカー選手になるという夢を叶えたのであった。
後編はこちら>>
広島で手にした栄光と、名古屋での苦闘。そして、古巣帰還で見出した新たなやりがい