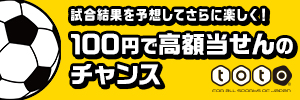「JJP」という言葉をご存知だろうか。「JFA/Jリーグ協働事業(JFA/J.League Cooperative Development Programme)」の略称で、JFA(日本サッカー協会)とJリーグが組織の垣根を越えて次世代の選手育成に投資していこうという試みだ。
2015年に立ち上がったこのプログラムは「フットパス」「国際経験」「全国指導者研修」「データベース」の主要項目から構成されており、それぞれの分野に予算を付けながら、新たな試みとして行われてきた。財源となったのは、もともとJリーグが日本サッカー協会に納めてきた「協会納付金(入場料収入の3%の納付義務がある)」を、このプログラムの予算として転嫁するというものである。背景にあったのは、当時の日本サッカーを取り巻く情勢がある。Jリーグの松永英機アカデミーダイレクターはこう振り返る。

「このプログラムの構想が持ち上がった2014年当時はU-17、20のFIFAワールドカップ出場を相次いで逃し、クラブレベルでもAFCチャンピオンズリーグでなかなか勝てないという状況が続いていました。そうした勝敗だけでなく、そもそも『タレントが育ってきていないのではないか』という疑問を多くの関係者が抱くようになっていた時期でした」
日本サッカーの育成を根本からブラッシュアップしていくこと。そうした大きな目標を立てた上で、いろいろな施策が立てられることとなった。「いま育成年代で能力のある選手の多くがJクラブを選んでくれるようになっているのは確か」(松永アカデミーダイレクター)という背景も踏まえながら、日本の育成を変えるにはJクラブがより良くなっていくしかないという視点を持ちながらの取り組みである。
なぜ勝てなくなったのか。あるいはなぜタレントが育ってこないのか。そうした疑問に対する明瞭な答えを出すのは難しいが、だからと言って何もしなければ何も進歩しようがない。クラブの育成システムを査定する「フットパス」などは完全に新しく、未知の試みだったために疑問を呈する声も少なくなかったが、「まずはやってみよう」(松永アカデミーダイレクター)というチャレンジだった。
「たとえば幼少期からの「国際経験」不足が敗因の一つにあるのではないかという見方は根強くあった。海外の異なる環境への適応はもちろん、サッカーのスタイルや個人の特長も国や地域によって大きく違ってくる。日本では感じられないスピード感やタフネス、あるいはリーチの違い、そして外国人レフェリーへの対応まで含めて、そうしたインターナショナルな対応力不足は、年代別日本代表監督からもしばしば挙げられる日本人の課題だった。その克服のために必要なのは選手も指導者も、これはもう経験するしかない」と(松永アカデミーダイレクター)。

このため、JJPは「国際経験」を一つの項目として掲げ、Jリーグ選抜やJリーグのアカデミーチームの海外遠征の予算を支援することに加え、国内での国際ユース大会実施も支援することとなった。Jリーグインターナショナルユースカップの拡充、JリーグU-16チャレンジを国際大会化などに加えて、クラブが主管している「COPA BELLMARE U11(湘南ベルマーレ主管)、「磐田U-12国際サッカー大会(ジュビロ磐田主管)」といった国際大会の開催支援も行うようになっている。Jリーグ・村井満チェアマンの言葉を借りれば、「国際試合が“当たり前”になる環境を作ること」を一つの大きな狙いとした試みであり、過去3年間でのべ150余りのチーム(およそ2,900名の選手)が「海外遠征」を経験することとなった。
ほかにも「データベース」を重要な項目として定義した。これまでフィジカル・テクニカルな選手個人のデータは、指導者個人が管理していることが多く、「ほとんどのクラブで、クラブとしてのデータベースを持っていなかった。このため、たとえばフィジカルコーチが辞めてしまうと、フィジカルのデータまで一緒になくなってしまうということがしばしばあった。当然、21歳の選手が13歳のときにどういう選手だったのかということも分からなくなっている」(松永アカデミーダイレクター)。

これでは「育成ノウハウの蓄積」ができなくなってしまう。たとえば、21歳で日本代表に入った選手がいたとして、その選手に対して13歳の時点で下していた評価が正しかったのか間違っていたのかという検証もできなくなる。失敗をフィードバックしてより良い育成を次代に施す、発掘し損なったタレントを発掘するといったこともできなくなってしまう。「総じて属人的で、組織としての蓄積がなかったのが、ここまでのJリーグの育成における最大の問題だった」(松永アカデミーダイレクター)という視点から、選手のデータベースをJJPで予算を付けて構築していくこととなった。これはJFAとも協働することで、年代別日本代表の選考などへの寄与も期待される。
「属人的に過ぎる」というのは一連の育成改革を語る上でのキーワードでもある。
「たとえば高校サッカーにも優れた指導者がたくさんいますよね。皆さんも小嶺忠敏先生(現・長崎総合科学大学附属高校監督)、先の全国高等学校サッカー選手権大会で優勝した山田耕介先生(前橋育英高校)など多くの名前を挙げることができるでしょう。彼らは何十年もの指導の経験からさまざまなノウハウを蓄積しています。ただ同時に、それらは指導者個人に属しているノウハウでもあります。指導者が替われば、リセットされてしまう可能性もあるでしょう。ましてやJクラブでは頻繁に指導者の交代が起きている現状があります。そうなると育成はぶつ切りになってしまう。そうならないために、クラブとして共通のフィロソフィーを持ち、クラブとして入ってきた“個”をどう育てていくのかという個別育成計画(IDP)や育成カリキュラムまで共有しておく必要があるのです。そのツールとしてデータベースが必要だということです。」(松永アカデミーダイレクター)
一般に「日本人は組織的」と言われがちだが、実は組織として取り組む部分こそ日本サッカーでおろそかになっていた部分ではないのか。JJPの各施策の中で浮かび上がってきたのはそうした疑問点である。ベルギーの機関に依頼して各クラブの育成のオーディット(監査)を行った「フットパス」もまた、そうしたクエスチョンとサジェッションをJリーグと日本サッカー界に提示することとなった。(後編に続く)